窓のカビ取り方法は?原因や放置するリスク、予防する方法も解説

窓に発生する黒いカビは、見た目の悪さだけでなく健康被害の原因にもなりかねません。放置すればアレルギーや修繕費の増加など、思わぬリスクもあります。
今回は、窓にカビが生える原因や放置のリスク、そして効果的な掃除・予防方法について解説します。
目次
窓のカビが発生する原因

カビは「温度」「湿度」「養分」「酸素」の4条件がそろうと発生しやすく、特に窓はカビの温床になりがちです。下記の表に条件をまとめます。
| 条件 | 説明 |
| 温度 | 20~30℃で活発に繁殖 |
| 湿度 | 60%以上で発生しやすい |
| 養分 | ホコリ・皮脂などがエサに |
| 酸素 | 空気中に常に存在 |
なかでも、結露は湿度を高める大きな原因です。放置すると窓枠にカビが発生しやすくなります。
【リスク大】窓のカビを放置するとどうなる……?
窓のカビを放置すると、見た目の不快感だけでなく、下記のような深刻なリスクがあります。
・アレルギーや喘息など健康被害の原因に
・壁紙やパッキンの劣化を早め、修繕費が増加
・カビの胞子が広がり、室内全体に被害が拡大
・賃貸物件では退去時の修繕費請求のおそれも
早めの対処が、快適で安心な住まいを守るカギです。
【場所別】窓のカビを取り除く具体的な掃除方法

窓のカビは、見た目が悪いだけでなく、アレルギーなどの健康被害の原因にもなりかねません。ここでは、家庭で発生しやすい窓周辺のカビについて、「ガラス」「サッシ」「木枠」「ゴムパッキン」の4つの場所ごとに、効果的な掃除方法を解説します。
窓ガラスのカビ取り
窓ガラスに発生するカビは、比較的落としやすい汚れです。そのため、特別な洗剤を用意しなくても、家庭にある道具で十分に対応できます。
主な手順は以下の通りです。
<窓ガラスのカビ取りの手順>
1.バケツに水を入れ、中性洗剤を少量加えて混ぜます。水と洗剤の割合は、目安として水1リットルに対して洗剤1〜2滴程度が理想です。
2.洗浄液を雑巾やマイクロファイバークロスに含ませ、窓ガラスをまんべんなく水拭きします。カビの黒ずみやくもりが気になる箇所は、軽く力を入れてこすりましょう。
落ちにくい場合は、スプレーボトルに洗浄液を入れて直接ガラスに吹きかけてから拭く方法も効果的です。
3.乾いた布で水分をしっかり拭き取ります。
掃除の際には「窓のサッシ」や「ゴムパッキン」に汚れが移らないよう注意が必要です。ガラスはキレイになっても、周囲にカビが残っていると再発の原因になりかねません。掃除後は風通しを良くするなど、湿気対策も心がけましょう。
窓のサッシのカビ取り
窓ガラスに比べて、サッシ部分のカビは取り除きにくいのが特徴です。特にアルミ製の溝部分や細かな角に入り込んだ黒カビは、布だけでは落としきれません。
以下の手順に沿って、サッシのカビ取りを進めましょう。
<窓のサッシのカビ取り>
1.掃除機や刷毛などでホコリを取り除いてから、水と中性洗剤を混ぜた液を使って歯ブラシや綿棒でこすります。
しつこいカビには、カビ取り用のジェルやペーストタイプの専用洗剤を使うのも効果的です。使用する際は、必ずゴム手袋を着用し、換気を十分に行ってください。
2.しっかりと水拭きし、乾いた布で水気を完全に拭き取ります。
湿気が残るとすぐに再発してしまうので、仕上げの工程は丁寧に行いましょう。
より詳しいサッシ掃除の方法は、下記の記事も参考になります。
「窓サッシの掃除方法は?原因やカビを落とす方法も紹介」
窓の木枠のカビ取り
木製の窓枠に発生したカビは、非常にデリケートな取り扱いが求められます。塩素系漂白剤や強力なカビ取り剤を使用すると、木材が変色したり傷んでしまうリスクがあるため注意が必要です。
以下の手順に沿って、木枠のカビ取りを進めましょう。
<窓の木枠のカビ取りの手順>
1.アルコール(消毒用エタノール)を染み込ませたティッシュや柔らかい布で、木目に沿ってやさしくふき取ります。
広範囲にわたる場合は、スプレータイプのアルコールを吹きかけて数分置いてから、乾いた布で優しく拭き取ります。
2.しっかり乾燥させ、窓枠の周辺の換気を行います。
カビの色素が残ってしまう場合には、木材専用のクリーナーや研磨剤を使う方法もありますが、表面を削ってしまう可能性もあるため、目立たない場所で試してから行いましょう。
窓のゴムパッキンのカビ取り
窓のゴムパッキンに発生したカビは、見た目の悪さだけでなく、放っておくと劣化の原因にもなります。ただし、ゴム素材はデリケートで、特に漂白成分を含む薬品を使うと弾力が失われたり、ひび割れたりする可能性があります。
ゴムパッキンのカビ取りは、以下の手順に沿って進めると良いでしょう。
<窓のゴムパッキンのカビ取りの手順>
1.カビ取り用ジェルタイプの洗剤を歯ブラシや綿棒に少量取り、ゴムパッキンの黒ずみ部分に塗りつけて数分放置します。
2.柔らかい布で拭き取り、乾燥させます。窓を開けて通気を確保し、パッキンの内側に水気が残らないようにしましょう。
窓のカビを予防するには

カビは発生してから対処するより、日常的に「発生を未然に防ぐ環境づくり」が重要です。ここからは、窓まわりにカビを発生させないための具体的な予防策を、日々の生活に無理なく取り入れられる方法とともに紹介します。
定期的に換気する
カビを防ぐ最も基本的で効果的な方法は、「定期的な換気」です。
窓まわりにカビが生える大きな原因は湿気。日常生活では料理や入浴、洗濯物の室内干しなどで湿気がこもりがちです。特に寒い季節は窓を閉めきることが多く、空気が滞留してカビが発生しやすい環境になります。
朝晩の10分程度でも窓を開けて空気を入れ替えることで、湿気を逃し、カビの発生を防ぎやすくなります。サーキュレーターを併用すると、より効率的に空気を循環できます。
部屋の湿度を60%未満に調整する
カビの好む湿度は60%以上ですので、除湿機やエアコンの除湿運転を活用して湿度をコントロールしましょう。特に梅雨時や冬場の結露が多い季節は、湿度が急上昇しやすいため、除湿機をタイマーで運転させるだけでも違いが出ます。
小型タイプならワンルームや子ども部屋にも設置しやすく、静音モデルも多いため、就寝中の稼働も安心です。
湿度計を設置して、目で見える形で湿度を管理するのもおすすめです。
結露防止用グッズを活用する
窓まわりのカビ発生の主な原因となるのが「結露」ですので、結露防止グッズの活用は非常に有効です。
例えば、結露防止シートは窓ガラスに直接貼るだけで断熱効果が高まり、結露の発生を抑えられます。貼るだけでOKなので、手間もかからず賃貸住宅でも使いやすいのが魅力です。
また、結露防止スプレーはガラスに吹きかけることで表面張力を変え、水滴がつきにくくなります。
結露対策について詳しくは次の記事もご覧ください。
「窓の結露対策7選!結露ができる原因や放置するリスクも踏まえて解説」
エタノールスプレーや中性洗剤を活用する
予防の一環として、週に1回程度の「エタノールスプレー」での除菌も効果的です。
アルコール(エタノール)はカビ菌を殺菌する効果があるため、乾いた窓枠やゴムパッキン部分にスプレーしておくことで、繁殖を抑えられます。
特に黒カビが発生しやすい窓枠のゴムパッキン部分については、汚れを拭き取るだけでなく、予防的に専用スプレーを使用することが効果的です。
さらに、汚れが気になる場合には、中性洗剤を用いた定期的な清掃により、カビの栄養源となるホコリや皮脂汚れを効果的に除去できます。
窓をリフォームする
根本的なカビ対策を考えるなら、「窓そのものをリフォームする」という選択肢もあります。
特におすすめなのが、下記のような断熱・防露性能の高い窓です。
・真空ガラス:ガラスとガラスの間が真空構造で、熱の伝導を抑える高性能ガラス
・複層ガラス(ペアガラス):2枚のガラスの間に空気層を設けて断熱
・内窓(二重窓):既存の窓の内側にもう一枚窓を設置して断熱・防音・防露効果を高める
断熱性能の高い窓にすることで、室温差による結露を抑え、カビが発生しにくい環境を作れます。
窓リフォームで根本的なカビ対策をするなら
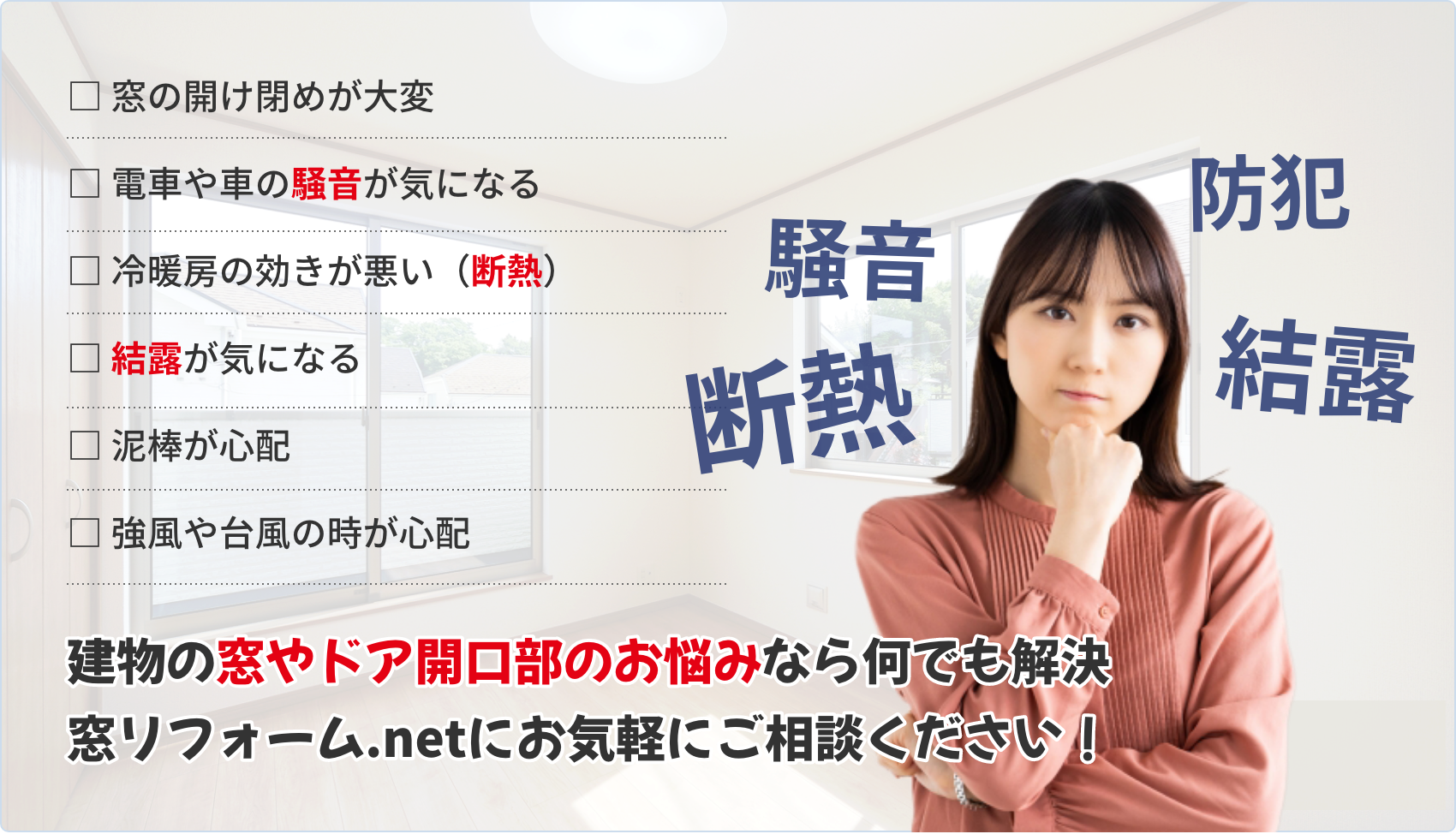
窓のリフォームを確実に、迅速に終わらせ、カビを根本的に解決したい方は「窓リフォーム.net」もご検討ください。経験豊富な職人が直接要望をヒアリングし、最適な施工を提案します。最短3時間のスピード施工で、忙しい家庭にも対応できます。
サービス詳細については、以下リンクからご覧いただけます。
まとめ
窓のカビは結露や湿気、ホコリなどが原因で発生し、放置すると健康被害や修繕費の増加につながります。カビの発生部位に応じた適切な掃除と日頃の湿気対策が重要です。定期的な換気や除湿、専用グッズの活用で、快適な住環境を保っていきましょう。

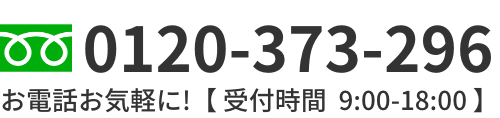




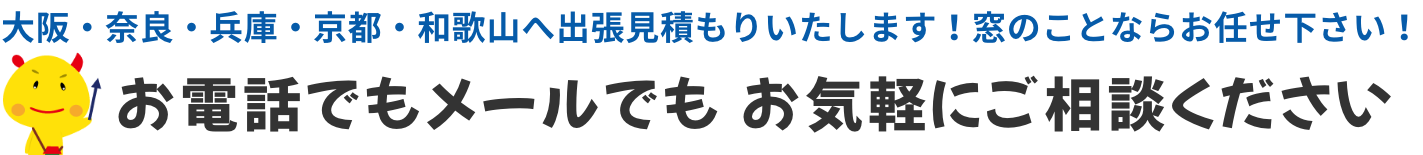
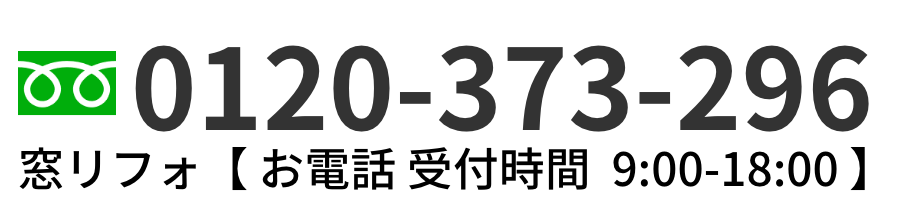
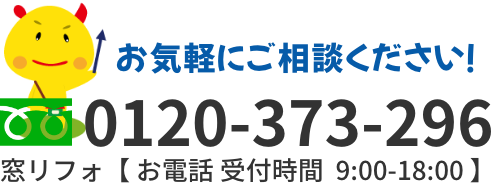
 リフォーム情報発信中!
リフォーム情報発信中!