窓の結露対策7選!結露ができる原因や放置するリスクも踏まえて解説

寒い季節になると、窓に結露が発生することがあります。窓枠などが濡れてしまい、「なぜ結露が発生するのか」「どうしたら結露を抑えられるのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、窓に結露が発生する原因や対策方法などについて解説します。
目次
窓に結露ができる原因

窓の結露は、外の冷たい空気によって窓表面の温度が低下し、そこに室内で発生した水蒸気が触れることで発生します。
つまり、「窓が冷たい」「室内の湿度が高い」という条件がそろうと結露が発生しやすくなるのです。窓に結露が発生する仕組みについて、さらに詳しく解説します。
窓に結露ができる仕組み
空気は温度の変化に応じて「飽和水蒸気量(空気が含むことができる水蒸気の限界の量)」が変化するという性質があります。
・空気の温度が上がる:飽和水蒸気量が増加する
・空気の温度が下がる:飽和水蒸気量が減少する
暖房などで暖められた空気が冷たい窓に触れると飽和水蒸気量が減少し、抱えきれなくなった水蒸気が水に変わって結露になります。
窓の結露を放置するのは危険!

結露で濡れた窓を放置すると、さまざまなトラブルが起こる場合があります。ここでは、窓の結露を放置した場合のリスクについて解説します。
カビやダニが繁殖する
窓の結露を放置すると、水分や湿気を好むカビやダニが繁殖しやすくなります。特に窓枠やカーテン、窓周辺の壁や壁紙などは、結露によるカビやダニの被害が出やすいため注意が必要です。
窓ガラスや窓枠に黒い斑点のようなものができていたら、それは「黒カビ」かもしれません。黒カビは湿度70%以上、温度20~30℃程度の環境を好むため、結露が多い窓周りは黒カビにとって理想的な環境なのです。
黒カビは奥深くまで根を張るので表面を拭いただけでは除去しきれず、すぐに再発します。再発を防ぐには塩素系漂白剤やアルコールなどを使って除去する必要があり、手間がかかって大変です。
また、繁殖した黒カビはたくさんの胞子を放出します。発生した黒カビを放置したまま窓を開閉すると、その度に部屋のなかに黒カビが舞い散り、喘息やアレルギーを発症する可能性もあります。
住宅の劣化につながる
窓の結露をそのままにしていると、水分や湿気が原因で窓周辺の壁や壁紙、柱、フローリングの床などが腐ってしまうこともあります。
特に木材をふんだんに使用している木造住宅は、木材が水分や湿気を吸収した状態が長引くと、木材が脆くなって住宅の耐久性が低下するリスクがあります。
また、マンションなどでは、窓ガラスやサッシに集中的に結露が発生しがちです。発生した結露が大量の水分となってサッシに溜まると、サッシが傷むおそれがあります。
窓の結露を抑えるための対策《7選》

結露を放置するとカビやダニが繁殖したり、住宅の劣化が進行しやすくなったりします。ここでは結露を抑える方法を紹介しますので、早めに対策しましょう。
こまめに換気する
こまめに換気して空気を入れ替えると、必要以上に室温や湿度が上がらなくなるので結露が発生しにくくなります。効果的な換気方法を紹介しますので、ぜひ試してみてください。
・1時間に2回を目安に窓を開ける
・複数の換気扇を同時に稼働させる
・サーキュレーターや扇風機で空気を動かす
・週1回を目安にクローゼットや押し入れの扉を開放する
かなり湿度が高い場合は、除湿機を併用するのがおすすめです。
冬場は室温が20度程度になるように調節する
屋外と室内の温度差が大きくなると、結露が発生しやすくなります。寒いからといって、室内を暖めすぎないようにしましょう。暖房器具を使う場合も、室温が20℃程度になるように設定するのがおすすめです。
窓に結露しにくくなるアイテムを貼る
窓に下記のような結露防止のアイテムを貼るのも効果的です。
・結露防止シート
・結露吸水テープ
・梱包用エアーキャップ(気泡緩衝材)
また、上記を用意できない場合は、窓のレールに新聞紙を挟むだけでも効果が見込めます。新聞紙に発生した結露を吸い取らせたら、ゴミとして処分しましょう。
窓に結露防止スプレーを吹き付ける
窓に結露防止のアイテムを貼るのが面倒な方は、結露防止スプレーを使ってみてはいかがでしょうか。窓に吹き付けるだけで済むので、余計な手間がかかりません。
市販の結露防止スプレーを購入しても良いですが、台所用洗剤などの中性洗剤を10ml、水を100mlの割合でスプレーボトルに入れれば自作できます。
窓用のヒーターを置く
窓表面の温度が下がると結露が発生しやすくなるので、窓用ヒーターを置いて窓の温度を上げるのもおすすめです。
窓用ヒーターを置くと窓からの冷気が軽減されて暖房効率が上がり、部屋が温まりやすくなるというメリットもあります。
除湿器を活用する
冬は乾燥しがちなので加湿器を使う方も多いでしょう。しかし、加湿器によって室内の湿度が上昇すると、窓の結露が発生しやすくなります。
結露が発生している場合は湿度が高すぎるので、加湿器ではなく除湿機を使いましょう。除湿機で部屋全体の湿度を下げれば、空気中の水蒸気が飽和水蒸気量を超えることがなくなるため、高い効果が期待できます。
窓をリフォームする
最近の住宅の窓は内窓(二重窓)になっていることが多く、昔に比べると結露が発生しにくい傾向にあります。古い住宅などで1枚窓のままの場合は、思い切って窓を内窓にリフォームすることを検討してはいかがでしょうか。
他の対策方法と比較すると費用がかかりますが、内窓にすれば結露対策アイテムを使ったり除湿機を設置したりしなくても結露が発生しにくくなります。ただし、賃貸物件では、許可なしで窓のリフォームはできないので注意しましょう。
内窓のリフォームなら窓リフォーム.netがおすすめ
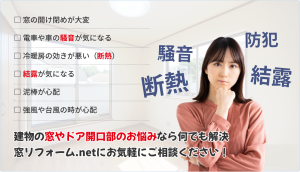
内窓のリフォームをお考えの方は、ぜひ「窓リフォーム.net」にご相談ください。「窓リフォーム.net」なら、15,750円~という低価格で内窓が設置できます。
熟練の職人によって、最短20分という短時間で完了するのも魅力です。さらに見積もりの担当者がリフォーム作業まで行うため、「見積もりのときに聞いた話と違う」などのトラブルが起こることもなく安心してご利用いただけます。
また、下記のような国や自治体が実施している助成金・補助金も活用可能です。
| 先進的窓リノベ2025事業 | 断熱性が高い内窓の設置・外窓の交換などを行った場合に費用の2分の1が補助される |
| 子育てグリーン住宅支援事業 | 断熱リフォームなど、所定の工事を行う場合に補助金が出る |
| 既存住宅における省エネ改修促進事業(東京都) | 省エネ性能が高く災害にも強い住宅にするために高断熱窓・ドアなどに改修した場合に補助が受けられる |
※2025年1月時点の情報です。詳細は公式ページ等をご確認ください。
「内窓を設置したい」「助成金・補助金を活用して窓をリフォームしたい」という方は、ぜひお気軽に「窓リフォーム.net」までお問い合わせください。
まとめ
冷たい外気に窓が冷やされると、室内の水蒸気が窓に触れて結露が発生することがあります。そのまま放置するとカビやダニが繁殖したり、住宅の劣化が進行しやすくなったりするため、今回紹介した内容を参考に早めに対策しましょう。

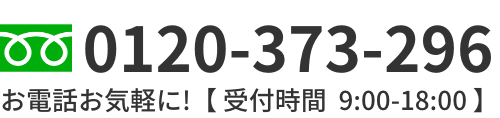




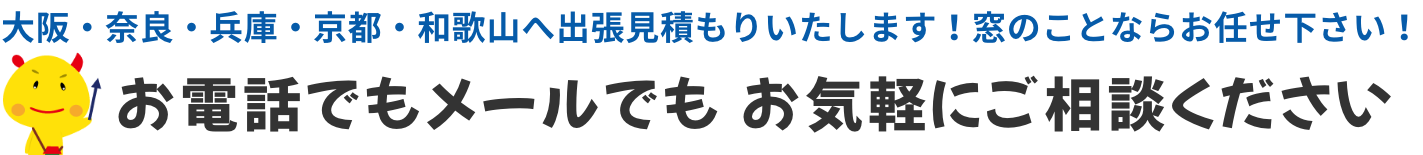
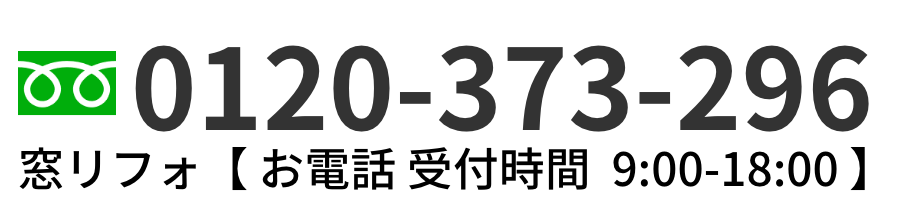
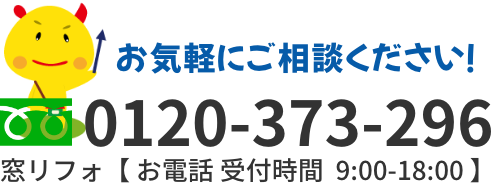
 リフォーム情報発信中!
リフォーム情報発信中!